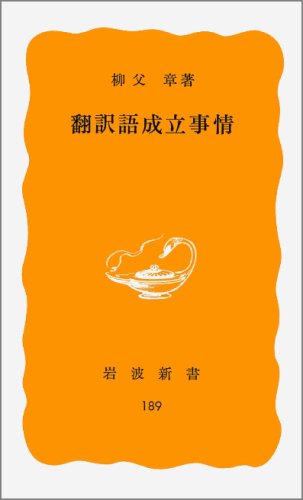緊急事態宣言~。
先月の。
印象に残った本
あえて『全体主義の起原』といわせていただきましょう。2月中には2巻・3巻も読めるといいわね。
読んだ本のまとめ
2021年1月の読書メーター
読んだ本の数:10冊
読んだページ数:2311ページ
ナイス数:152ナイス
https://bookmeter.com/users/418251/summary/monthly
■全体主義の起原 1 ――反ユダヤ主義
この第一巻では、ナチズムを形成せしめた要因の一つとしての反ユダヤ主義が扱われる。中世までの反ユダヤ主義と近代の反ユダヤ主義とに切断線を見出し、国民国家の形成過程、あるいは産業資本主義の発展過程のなかで、ユダヤ人が独特の地位に置かれるようになったことを跡付け、またフランスにおける(カトリックを背景とした)反ユダヤ主義の破産の現れとしてのドレフュス事件を論じて次巻につづく。プルーストの読解のくだりは大変面白く読みました。
読了日:01月10日 著者:ハナ・アーレント,大久保 和郎,ハンナ アーレント,Hannah Arendt
https://bookmeter.com/books/12747
■翻訳語成立事情 (岩波新書 黄版 189)
「社会」や「個人」、「近代」などの明治以降の造語から、「自然」などの翻訳語として機能するようになった語を取り上げ、それらの用例から、どのように意味が彫琢されていったのかを簡潔に跡付ける。翻訳の過程で意味が薄められ、ある意味なんとなく(漢字のものものしさを背景に)使用されていく「カセット効果」についての議論はなるほどなという感じ。
読了日:01月10日 著者:柳父 章
https://bookmeter.com/books/457777
■苦学と立身と図書館 パブリックライブラリーと近代日本
なぜ学生は図書館で勉強するのか?という問いに歴史的なアプローチでもって答えようと試みる。近代日本社会における図書館は、アメリカ的な公共図書館をモデルにしつつも、蔵書によって学問をする場所である近世の「文庫」ともある種の連続性を指摘する。近代読者成立の文脈ではなく、立身の空間としての公共図書館というようなかたちで図書館のありようを跡付けた労作と思います。斜め読みなんであれなんですけど。
読了日:01月10日 著者:伊東 達也
https://bookmeter.com/books/16438067
■ジョゼと虎と魚たち (角川文庫)
同名アニメ映画公開を機に再読。原作に大きく要素を付け足している映画版ではあるが、セクシャルな要素の実際的に乾いた感じと、それと同居する生々しさ、そしてどことなく漂う死の香りみたいなものははっきりオミットされていたよな、とも感じる。全体として、関西弁の音の響きが魅力的なテクストであるなあと。
読了日:01月10日 著者:田辺 聖子
https://bookmeter.com/books/559996
■越境者的ニッポン (講談社現代新書)
海外在住の博奕打ちからみた、日本列島社会のおかしさを指摘する連載の書籍化。自身の子どもがオーストラリアの教育(をになう人々)によっていかに助けられたか、という挿話が非常に印象的。オーストラリアの多文化主義については近年ある種の能力主義を隠蔽する口実になっているとの批判もあると思うが、こうした良心をもった公務員によって内実が担保されてるのだなと。
読了日:01月14日 著者:森巣 博
https://bookmeter.com/books/413091
■はじめてのスピノザ 自由へのエチカ (講談社現代新書)
100分de名著に加筆して新書化したもの。スピノザの自由概念などの説明を読むと、國分功一郎の仕事は『スピノザの方法』から『中動態の世界』まで連続しているのだなと思う。古田徹也『それは私がしたことなのか』などの仕事と対比すると、國分vs.古田のような構図がぼんやりと頭に浮かんでくる。
読了日:01月16日 著者:國分 功一郎
https://bookmeter.com/books/16964330
■社会学講義 (ちくま新書)
1993年発行の別冊宝島から抜粋、加筆したもの。「家族社会学」の章のみ書き下ろし。元々は20章、本書は6章。大澤真幸や吉見俊哉、若林幹夫と錚々たる書き手のテクストでミーハーな読者の興味を惹き、「社会調査論」の佐藤郁哉が締めるのは、近年の社会学のトレンドへの目くばせもしてまっせ、みたいな計らいだろうか。大澤の「社会秩序はいかにして可能か?」という問いが全編を律しているような気もして、存外まとまりのあるよい本です。
読了日:01月17日 著者:橋爪 大三郎,大澤 真幸,若林 幹夫,吉見 俊哉,野田 潤,佐藤 郁哉
https://bookmeter.com/books/11117654
■演劇入門 (講談社現代新書)
戯曲を書く、という実践を通して、演劇からみる世界とはいかなる手触りを持つものなのか、ということを語ろうとする。書き方のハウツーは非常に具体的で、人物間の情報量の差を設定して対話の中で観客に情報を提示する、などはシステマチックな技術を開陳しつつ、他者とこのわたしとの関係の問題として演劇的な対話の重要性を説く、腰の座った思想の書でもあらんとする堂々たる語り。おもしろく読みました。
読了日:01月26日 著者:平田 オリザ
https://bookmeter.com/books/460459
■僕たちは戦後史を知らない――日本の「敗戦」は4回繰り返された
「戦後史を知らない」のは、単に読むべき本を読んでないからではないですか。戦後史を語ろうとする本書が、たとえばダワー『敗北を抱きしめて』であるとか、小熊『<民主>と<愛国>』であるとか、そうしたある種の基本文献を参照した形跡が認められないことは、本書の前提そのものを危うくし、結果本書が語るのは蓄積された歴史研究から遊離した「ファンタジーの戦後史」に陥ってるようにしか思えません。怠惰と思いつきで書かれたテクストに付き合ういとまは、わたくしには残念ながらありません。
読了日:01月26日 著者:佐藤健志
https://bookmeter.com/books/7765568
■なぜ歴史を学ぶのか
フランス革命を専門とする歴史家が、21世紀における歴史学の位置と使命を語る。歴史学そのものというよりは、偽史と流言が飛び交う現代社会のなかで歴史学の果たしうる機能について書き記したコンパクトな書物。ポストコロニアル的な思潮の展開の中での歴史学の変容などにと触れられ、そういう意味での近年のトレンドへの目配りは啓蒙的で勉強になります。
読了日:01月30日 著者:リン ハント
https://bookmeter.com/books/14497494
近況
薄暗がりにうごめくもの——『パラサイト 半地下の家族』感想 - 宇宙、日本、練馬
朝鮮半島の怒りのデス・ロード——『新感染半島 ファイナル・ステージ』感想 - 宇宙、日本、練馬
アニメ『THE IDOLM@STER』感想 - 宇宙、日本、練馬
裂けた自意識——アニメ『モブサイコ100』感想 - 宇宙、日本、練馬
来月の。